はじめに
攻撃はゼロデイ、サプライチェーン、生成AIを悪用したフィッシングへと拡張し、人手だけでは監視・解析が追いつかない時代になりました。最新のセキュリティ運用では、AI/LLMを用いた脅威検知・自動トリアージ・レスポンスの高速化により、検知精度と運用効率の両立を図ります。本記事は、検知・自動対応・評価・ガバナンスまでを実務視点で整理します。
検知:ログ・ネットワーク・エンドポイントを横断するAI分析
- 異常検知:ネットワークフロー、DNS、認証、EDRの信号を統合し、Isolation Forest / One-Class SVM / Autoencoderで異常振る舞いを検出。
- 意図理解:LLMでログを自然言語要約、MITRE ATT&CKとの照合により戦術レベルで脅威を可視化。
- 脆弱性連携:脆弱性スコア(CVSS)× 露出(インターネット公開/権限)でリスク優先度を算出。
自動対応:SOAR × LLMでトリアージとワークフローを高速化
- プレイブック自動化:隔離・ブロック・パスワードリセット等をチケット化。LLMが事実抽出と要約でアナリストの判断時間を短縮。
- 根拠付き推奨:IoC、関連ホスト、時系列の因果を提示し、ヒューマンインザループで承認。
- 復旧標準化:スナップショット復元、端末初期化、証跡保全を手順化。SLAに連動した優先度制御。
関連記事:
LLMにおけるデータ漏洩リスクと防止策
ゼロトラスト運用:リスク自動評価と動的アクセス制御
- コンテキスト認証:端末健全性・位置・時間帯・振る舞いをスコア化し、MFA/段階的制限を自動適用。
- 最小特権の継続評価:利用実態に応じた権限縮小、機密データへのアクセスはJIT(Just In Time)。
- 監査ログ:入力・出力・ベクトル参照・ツール呼び出しを改ざん不可で保存し、説明可能性を担保。
評価とモニタリング:精度だけでなく運用コストを下げる
- メトリクス:検知率/偽陽性率/MTTD/MTTRに加え、調査コスト/件、自動解決率を追跡。
- レッドチーム:プロンプトインジェクション、データ抽出、役割逸脱の攻撃試験を継続。
- ドリフト監視:問い合わせ分布や攻撃手口の変化を検知し、ルール/モデルを定期更新。
ガバナンス:ポリシー・責任分界・データ保護
- データ境界:機密・個人情報はマスキングし、外部モデルへの送信を制限。隔離テナントとKMS暗号化。
- 責任分界:自動化の範囲/人間承認の境界を明文化。高リスクは必ずヒトが最終承認。
- モデル管理:バージョン凍結、ABテスト、脆弱性対応と再学習の手続き化。
まとめ
AIは、検知精度の向上と運用効率の両立を実現します。鍵は、SOAR/LLMを活かした自動化、ゼロトラストに基づく動的制御、そして説明責任を満たすガバナンスです。Rudgleyは、AI × セキュリティの実装で貴社の運用高度化をご支援します。ご相談はこちら。







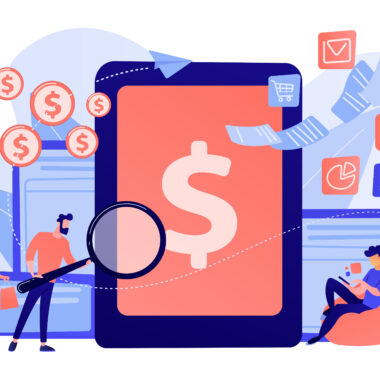







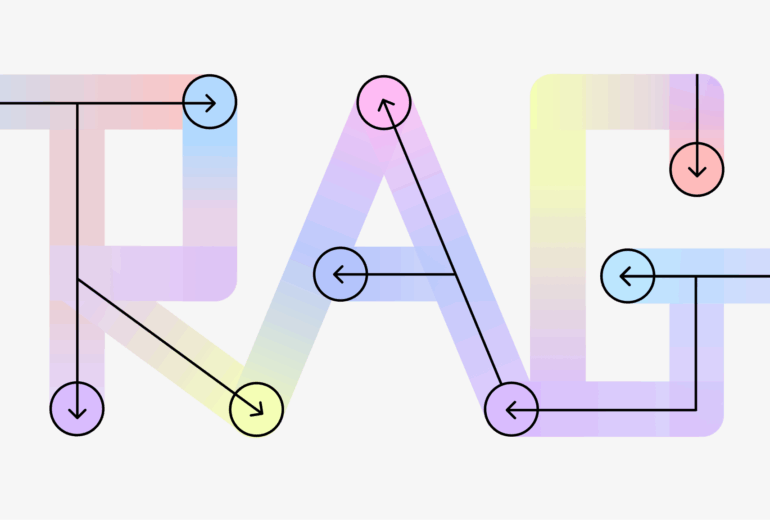


コメント